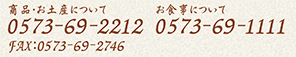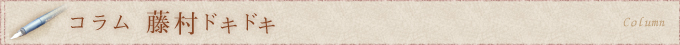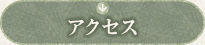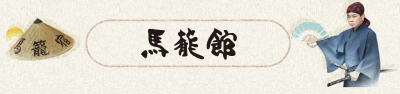- 中国と台湾と島崎藤村
- 2016年02月08日
旧正月のお休みを利用して中国・台湾・香港・シンガポール、韓国、そして移民としてアメリカやカナダ、ヨーロッパ各地に渡った方、そして仕事でアフリカで活躍されている方等が「春節」の前後1ヶ月程の時期に沢山の方が訪日され、空港やデパート、日本各地の観光地が賑わっているという報道を目にします。
アジアの歴史が「観光」を通してまた新しい時代の1ページを開きつつあるのかな?と思います。
Wi-Fi環境の整備やスマートフォンの保有率が上がるにつれて、「旅のスタイル」や「旅の準備」「旅行中に楽しみたい事」も激変しつつありますが、渡航手段として「客船」が主だった古き良き時代は「手紙」や「本」「万年筆」等は旅を彩るまたとない「知的な小道具」だったと思います。
そして渡航先の情報収集やイメージを膨らます情報源は「活字」「印刷物」が担っていた時代です。
異国情緒を楽しみたい・・・かの国の文豪の翻訳本をカフェで読みふける・・・そして自分の中で旅先のイメージを沸き立たせていたと思います。
さて、現代ではどれ程の人が「これから旅行する国」の事をかの国の文豪の名作を読んでイメージを膨らませる・・といったえらく時間と手間がかかる方法で「かの国」の事を知ろうとする事を実践されているのか?はミステリー的な数値となると思いますが・・・もしこのブログを読んでいる方で「それをやってみたい」という方がいるかも知れませんので??・・・春節旅行の方向けのお話になります。
島崎藤村の小説で中国語に翻訳されたものに「破壊」という小説があります。
馬籠宿の話や暮らしぶりだけでなく、当時の日本の全体の暮らしや時代描写に優れた、また島崎藤村自身にとっても作家として大いなる転機となった重要な作品です。
英語(=欧米向け)に翻訳された「夜明け前」に対し中国語(=アジア向け)に翻訳された「破壊」。
英語・中国語・日本語を理解できるバイリンガル・トリリンガルの方は是非この2冊の原作・翻訳本を読み比べ、そして何故この本が翻訳本として選ばれたのかな?を考察されるのも「研究のお題」となるやもしれませんね。
そして、またこんな話もネットで拾い上げました。
島崎藤村が本名で書いた手紙を始め、日本の文豪達が日本の大正時代から昭和にかけての激動期に中国の作家、魯迅の弟「周作人」(1885~1967)に宛てた多くの手紙が中国で発見された、という話です。
周作人は明治時代に魯迅とともに来日。帰国後に大学教授として日本文学を研究。日本の文豪と交流があり、書簡は北京在住の孫が保管していたそうです。
弘前学院大学大学院の顧偉良教授が今後調査を継続される、とありました。
余談ですが魯迅は島崎藤村との縁深い仙台の東北大学の「旧仙台医学専門学校」で1年半ほど学んでいます。
また、こんな話もあります。
島崎藤村との縁深い小諸市では「中国藤村文学賞交流」として南京大学との交友を深めています。
さて、藤村と台湾の繋がりについては?というと・・・より私的、個人的な話になってきます、
そして、より女性的な繊細な、話に繋がってゆきます。
其れゆえに、藤村にとっては台湾とは親しい人が「大切に新しい生き方ができる」場所、そして「そっとしておいてあげれる」場所として「最も大切な場所」としていたのではないのでしょうか?
そんな藤村の台湾への思いは藤村の個人体験を赤裸々に綴った「新生」という小説で綴られています。
「藤村に繋がる台湾」については神戸大学大学院文化学研究科 張, 錦華さんの研究論文によって新しい事実がいくつも綴られています。
またひとつ・・台湾国内で藤村ゆかりの足跡を辿る場所を海外の方に見つけて頂いた様です。
作:とざそし まき