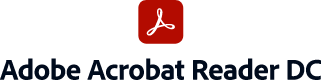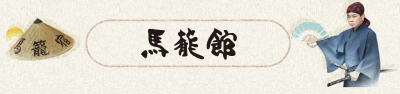- フランスの家
- 2015年06月06日
梅雨に入る前の爽やかな日々。
南ヨーロッパの「夏」の様な自然が恵那山や木曽の山々に広がっています。
フランスのタイヤメーカーのミシュランが発行しているミシュランガイドからも星を頂いている木曽谷や馬籠宿。
ので、そんな美しい恵那山の景観を眺めつつ、今日は藤村のフランスでの日々についてちょっと書いてみます。
藤村が諸般の事情でフランスに神戸から渡航したのは1913年5月。
そして1916年4月に帰国するまでの約3年間、藤村はフランスに滞在しています。
初めはパリに滞在し、滞在中の様子は1913年8月27日から1915年8月30日まで「仏蘭西だより」と題し、120回に渡り紀行文を東京朝日新聞に寄稿しています。
その寄稿の中で、パリ滞在中にガヴォー音楽堂で催されたドビュシー本人の演奏を聴き「非常に渋い」とその時の感想も書いています。
また「海へ」「エトランゼエ 仏蘭西旅行者の群れ」等の書籍にもフランス滞在時の彼の心情が良く描かれています。
1914年7月に第一次世界大戦が勃発し、藤村は「下宿屋のマダム シモネ」の勧めでパリ南東400Km程にある、リモージュ市にあったマダム シモネの姉の家へ11月まで疎開をしました。
この家は現在はリモージュ市によって「特別保存家屋」に保護指定され、ガイドブックにも掲載されています。(居住家屋の為内観は不可)
家屋の表に藤村滞在を記す銅板が取り付けられた家は駅から徒歩20分程、ヴィエンヌ川の近くの高台にある19世紀末の建物。
また、藤村滞在の縁でリモージュ大学と藤村の母校、明治学院大学の間では交換留学が行われているそうです。
フランス滞在当時の藤村は故郷の木曽の山々で見慣れた「トチの木」の花に似た「パリのマロニエの並木路」を眺めると馬籠を思い出したりして、「異国にたったひとりで暮らす東洋人の私」とじりじりと激しく、それと正面から向かい合い、深く我に問いかけていたのだと思います。
異邦の地で迎えた「世界大戦」の体験は帰国後に発刊した、馬籠を題材にした「夜明け前」「破壊」等の大作の中で「次第に影を落として行く時の流れ」として描かれている様に思います。
日本ペンクラブ初代会長就任後の1935年に藤村はアルゼンチンで開催された国際ペンクラブ大会に出席後、帰路の際に再度フランスに立ち寄りました。
その旅の体験は絶筆となった「東方の門」で、異国から見た「日本人の粘着性、故のアジアにおける我が国の高い運命」として描かれる筈であった作品に繋る筈でした。
藤村が何を描ききりたかったのか?知りたいな、と思います。
作:とざそし まき