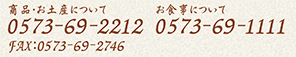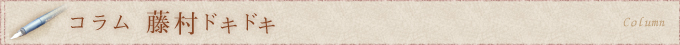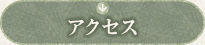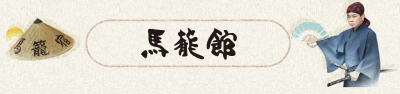- 卒業写真
- 2014年03月17日
馬籠宿にも平地より少し遅い春の気配が漂ってきました。
3月は年度末にあたり、旅立ちをされる方も多いのではないでしょうか?
いろんな旅立ちがあると思いますが、「さようなら」の瞬間に流れていた曲は生涯忘れられない思い出になると思います。
そして馴染んだ土地を離れて、新しい未来への挑戦が始まる決意や覚悟をする、といった大きな節目を乗り越えてゆく時に人は自然に大きな成長を遂げるのだと思います。
人生の節目のひとつに「卒業」がありますが、卒業式に流れる校歌は妙にその詩の語の意味を噛み締めてみたり、今まで感じなかったけど結構いい歌だなと思ったりして、感慨深げな気持ちになります。
近年ちょっと有名な校歌といえば、ユーミンこと松任谷由実さんが荒井由美の時代に作詞作曲した長崎県五島島列島の五島島高校の校歌「瞳をとじて」でしょうか。
ちょっと羨ましい校歌ですね。
さて、明治時代に西欧文化に追いつけ追い越せ、と多くの学び舎が次々と開校され、文系、理系大学の他外国語、音楽、美術等の大学も近代日本の未来を支える若者達に広く学習の門度を開いてゆきました。
島崎藤村もその新しいタイプの学校に進学し、近代日本文学の礎を大きく刻んだ一人となりました。
文壇デビュー後暫くは「詩人」の道を歩んだ藤村ですが、最後の詩集「落梅集」を最後に「詩」から「文学」へ大きく舵切り替える時に、藤村は自らの「詩」の集大成として、ひとつの校歌の詩を書き上げています。
それが自らの卒業大学「明治学院大学」の校歌です。
その詩を読んでみると、藤村から若者への強いメッセージが込められている事が分かります。
そしてそれは、自身への詩人としての成功にあぐらをかく事に甘んじず、文学という自身にとってリスクを伴う未知の分野への挑戦を始める、自分への応援歌だった様にも思います。。
藤村の文学全集には収められる事が無い詩なので、普段は目にほとんど留まらない作品だと思いますので・・ちょっと、書き出してみましょう。
人の世の若き生命(いのち)のあさばらけ
学院の鐘は響きてわれひとの胸うつところ
白金の丘に根深く記念樹のたてるを見よや
緑葉は香ひあふれて青年(わかもの)の思ひを伝ふ
心せよ学びの共の新しき時代(ときよ)は待てり
もろともに遠く望みておのが志(じ)し道を開かむ
そらあらばそらを窮(きわ)めむ壌(つち)あらば壌にも活きむ
ああ行けたたかえ雄雄志(おおし)かれ
眼さめよ起てよ畏(おそ)るるなかれ
不思議に何度でも読み返したくなる詩ではないでしょうか?
その他藤村は仙台、小諸、等藤村とゆかりが深い各地の学校校歌の詩の補作を沢山手がけています。
藤村の生誕地、馬籠宿の近くでは恵那高等学校の校歌の補訂を手がけています。
こちらの校歌にも新しき時代の使命は重くそれをうち建てよう、と呼びかけられています。
また藤村没後ですが中央大学学生歌「惜別の歌」は藤村の詩集「若菜集」に収監されている「高楼」という詩に曲が付けられた歌です。
この歌は終戦前の最も第二次世界大戦が激しかった時に学徒動員で戦地に赴く事なった友人の大学生達を送る歌として終戦まで歌われ続けた歌だそうです。
惜別の歌は戦後の昭和26年に新潮社で「島崎藤村全集全19巻」の編集責任者であった藤村の息子さんの承諾を得てレコード化されています。
希有な才能を持った人物の精神はいつまでも時代を超えて新しい時代の若者に響き、いつも「今、ここに」開花し続けているのだと思います。
コラムニスト:とざそし まき